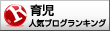第4回親子学級[2009年10月21日(Wed)]
第4回親子学級
「子どもの発達に遊びが大切なワケ」
今回は、帝京大学で幼児教育や発達心理学などの講義をされている教授の杉本真理子先生からお話を伺いました。
まず、現在の幼稚園・保育園の状況についてお話がありました。子供達が鯉のぼりを一つ作るにあたっても、印刷された紙を指定されたとおりに切り抜いて指定されたとおりの色を塗るように指導する園もあれば、プールに放った鯉を園児一人一人が1匹ずつ捕まえてその体験を元にして鯉のぼりを作れるよう環境を整えてくれる園もあるそうです。
そして、絵本を実際に先生に読んでいただき、絵本の読み聞かせの大切さについてお話を伺いました。
・心を育てる本を親は選んであげなければいけない
・本屋の売るための細工にのらない
・ゆっくり読む(今の3倍・5倍の時間をかけてじっくり読む)
・文字を読めるようになった子供に対しても「もう読めるでしょ」とは言わない
・子どもは絵本を通して親との関わりを求めているから何度でも同じ本を読んであげる
・絵をじっくり見せるようにする(字が読めてしまうと字だけ読んでめくってしまう)
・絵本には精神性の高いテーマがある
また、年齢にあった本を読んであげようというお話もありました。
1〜2歳:「どうぶつのおやこ」ストーリーはなく、子どもがいてお母さんが出てくることの繰り返し
2〜3歳:「3びきのくま」「3びきのこぶた」「3びきのやぎのがらがらどん」繰り返しの物語
3〜4歳:「ももたろう」「ちからたろう」出世物語 成長を感じる
5〜6歳:「スーホの白い馬」複雑な人間関係を知る
権力の言いなりになるのが正しいのかを考える
先週観た映画でアリサが卒園時に読んでもらっていた
「黄金のかもしか」も権力に立ち向かう話
そして、「遊び」と「学び」の関係についてお話がありました。
「勉強」とは中国語で「ガマンする」という意味がある。つめこまれてばかりいては自ら頭を使って考えたり理解することができなくて、ガマンして苦しいだけの「勉強」になってしまう。幼児期に遊びが充実していれば、遊びの中における経験を重ねながら自ら想像し考えて理解を深めて「学び」ができる、ということでした。
次回は「外で遊んでる?」というテーマで、親子で一緒に外遊びの会代表の久保浩子さんにお話を伺います。
 保育室だより第3回分を載せました。
保育室だより第3回分を載せました。
 ブログ担当のつぶやき
ブログ担当のつぶやき
普通に朗読したら3分かからないような絵本を20分かけて子供とやり取りしながら読み聞かせをした話を先生から伺い、自分自身が絵本を「読む」ことに意識がいっていて「子供とのやり取りを楽しむ」ことが少し欠けていたなぁと感じました。書かれている文字だけが全てじゃないんですものね。
ところで、皆さんのパパは絵本を読むのが上手でしょうか?うちは笑えるくらい下手です 書かれている文字を一言一句変えることなく余計な言葉も抑揚も無く読むんです
書かれている文字を一言一句変えることなく余計な言葉も抑揚も無く読むんです 今回の講座で私が感じたことを是非パパにも伝えたいと思いました
今回の講座で私が感じたことを是非パパにも伝えたいと思いました
「子どもの発達に遊びが大切なワケ」
今回は、帝京大学で幼児教育や発達心理学などの講義をされている教授の杉本真理子先生からお話を伺いました。
まず、現在の幼稚園・保育園の状況についてお話がありました。子供達が鯉のぼりを一つ作るにあたっても、印刷された紙を指定されたとおりに切り抜いて指定されたとおりの色を塗るように指導する園もあれば、プールに放った鯉を園児一人一人が1匹ずつ捕まえてその体験を元にして鯉のぼりを作れるよう環境を整えてくれる園もあるそうです。
そして、絵本を実際に先生に読んでいただき、絵本の読み聞かせの大切さについてお話を伺いました。
・心を育てる本を親は選んであげなければいけない
・本屋の売るための細工にのらない
・ゆっくり読む(今の3倍・5倍の時間をかけてじっくり読む)
・文字を読めるようになった子供に対しても「もう読めるでしょ」とは言わない
・子どもは絵本を通して親との関わりを求めているから何度でも同じ本を読んであげる
・絵をじっくり見せるようにする(字が読めてしまうと字だけ読んでめくってしまう)
・絵本には精神性の高いテーマがある
また、年齢にあった本を読んであげようというお話もありました。
1〜2歳:「どうぶつのおやこ」ストーリーはなく、子どもがいてお母さんが出てくることの繰り返し
2〜3歳:「3びきのくま」「3びきのこぶた」「3びきのやぎのがらがらどん」繰り返しの物語
3〜4歳:「ももたろう」「ちからたろう」出世物語 成長を感じる
5〜6歳:「スーホの白い馬」複雑な人間関係を知る
権力の言いなりになるのが正しいのかを考える
先週観た映画でアリサが卒園時に読んでもらっていた
「黄金のかもしか」も権力に立ち向かう話
そして、「遊び」と「学び」の関係についてお話がありました。
「勉強」とは中国語で「ガマンする」という意味がある。つめこまれてばかりいては自ら頭を使って考えたり理解することができなくて、ガマンして苦しいだけの「勉強」になってしまう。幼児期に遊びが充実していれば、遊びの中における経験を重ねながら自ら想像し考えて理解を深めて「学び」ができる、ということでした。
次回は「外で遊んでる?」というテーマで、親子で一緒に外遊びの会代表の久保浩子さんにお話を伺います。
普通に朗読したら3分かからないような絵本を20分かけて子供とやり取りしながら読み聞かせをした話を先生から伺い、自分自身が絵本を「読む」ことに意識がいっていて「子供とのやり取りを楽しむ」ことが少し欠けていたなぁと感じました。書かれている文字だけが全てじゃないんですものね。
ところで、皆さんのパパは絵本を読むのが上手でしょうか?うちは笑えるくらい下手です