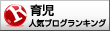16年度 第9回親子学級[2016年11月02日(Wed)]
2016年度 第9回親子学級
『もう知らなかったじゃ済まされない!ネットコミュニケーションマナー』
今回は親子スマイルネットの佐藤安南さん、鵜飼絵美さんにお越しいただきました。
映像ディレクターとしてお仕事をされている佐藤安南さんには、昨年「メディアから見た現代の子育て事情」というテーマで、一昨年は「メディアから見た現代の子育て家庭」というテーマでお話を伺いました。
LINE、Facebookなどのツールを誰もが使うようになった昨今、「ママ友とのLINEで返信の早さについていけない」など悩むママも多いため、ネットでのコミュニケーションについてお話を伺いました。
■ネットコミュニケーションにまつわる悩み・疑問
・キラキラしているママ友の写真を見て羨んだりして疲れたり、人に影響されたりしないように、SNSはやらない。以前はサークルなどの関係で朝から50件ほどメッセージが入っていたこともあるが、それを読んだりするのが大変なので抜けた。
・複数人に送られた一つのメールに対して、同じ用件なのに別の題名に変えて返信してくる人がいて異なるスレッドが立って困ったことがある。
・LINEにママ友の写真を載せて抗議されて、それまでのやりとりをすべて削除した人が周りにいる。
・昔、Mixiでコメントしなかったことを友達に怒られてやめた。
・LINEは既読が分かるから、すぐに返信できない時は読まないようにしている。
すぐ返信出来ない時にLINEをうっかり既読にしてしまったら、独身の友達と険悪になった。
・スマホをいじっていると子どもが構って欲しがる→子どもを怒ってしまう→主人に怒られる。
・結婚前にMixiをやっていたが返信が大変で指が痛くなった。
・同じ年齢の子どもを持つ女性芸能人のブログを見るように旦那に言われ、そのブログの情報と自分を比べられるのが嫌だ。
・グループLINEで「うちの子○○できるようになったよ」とそれぞれがコメントすると、グループ全員に対して返信を返さなければならず、コメント数が増えてしまって大変。
■インターネットの基本情報(総務省発表)
・世界のネット人口:34億9千万人 → これだけの人から見られる可能性がある。
・ネット利用端末:1位 パソコン、2位 スマホ・・・若い人ほどスマホ → 子どもにも教育が必要。
・インターネットの利用目的:1位 ソーシャルメディアの利用(SNS、YouTube、検索)
・ソーシャルメディアの利用目的:人とのコミュニケーション
・日本でのソーシャルメディア利用率:1位 LINE、2位 Facebook
・世界のLINE利用人口:2億人(10〜20代) → 年代によって使うツールが違う
・世界のインスタグラム利用人口:5億人(20代女性がメイン) → 変な写真は載せない!
メール・LINE・SNS → ネット上の「文字」のコミュニケーション
■インターネットでの心得
自分のペースで使えばいい(自分を主体にする)
返事をしないと嫌われるかも→なんで嫌われたくないのか、その人とどうなりたいのか?SNSをどう使いたいのかを自分から発信することも必要。実際に会ったときに宣言する。
ネット上に流れる情報は鵜呑みにしない
インターネット上に乗っている情報は間違いが多い。子育て情報、幼稚園情報など鵜呑みにしない。学校でも宿題の調べものをするのにインターネットを使用してもいいことになっているが、市や区の運営してる公式なサイトのみが許可されている(他のサイトは信用できない)。
子どもは教育されているが、親世代はネット教育を受けていない。
自分で考えて自分で決める
人とのコミュニケーションは直接話すことが大切。
グループメッセージの利用について
文字を書くのが上手な人と下手な人がいる(=誤解が生まれる)という大前提を認識すること。
おしゃべりと連絡事項の違い
LINEなどでは「○月○日に△やります!」という大切な情報を発信しても、「参加します」などのコメントが増えるほど、当初発信した大切な情報がどんどん埋もれていってしまう。
<ツールの使い分け>
・おしゃべり用のLINEグループと連絡用のLINEグループを分けて作る
・おしゃべり用はLINE、連絡用にはメールを使うなどしてツール自体を使い分ける
・どうしても使い分けできない場合は、埋もれた情報を掘り起こして再度発信する。埋もれて分からなくなった情報を放置せずにきちんと質問する。
<文章の使い分け>
・先生など目上の人を相手にスタンプ一つで返信を終わらせるのは失礼。言葉遣いを考えて文章を書く。
・大切な連絡事項は誰もが読みやすいように箇条書きにする。
■SNSを使うなら知っておきたいこと
<LINE、Facebookなどのツールが無料な理由>
私たちが個人情報を載せている(=個人情報を提供している)
↓
ライフスタイルに見合った広告が掲載される
↓
企業は広告で収益を得ている
<公開範囲の設定>
情報の公開範囲の設定をしないと、見ず知らずの誰でもが閲覧できる状態になっている。誰と誰がつながっているか等の情報が公開されることによって、オレオレ詐欺などで悪用され、自分とつながっている周りの人が迷惑を被ることもある。
海外では子どもが「自分の小さい頃の写真をインターネット上から削除して欲しい」と訴訟を起こした事例もある。親は子どもが可愛いからといって色々な写真を載せたりしがちだが、子ども自身もネットを使うようになっている。
■メールを使うなら知っておきたいこと
3種類の宛先を正しく使い分けないと個人情報漏えいにつながる。
To(読んで欲しい相手)
Cc(カーボンコピーの略:コピーとして送りたい・知らせたい相手)
Bcc(ブラインド(見えない)で送りたい相手、不特定多数に送る時などに使用)
もらったメールに返信する時も、メールをくれた人だけに返信するのか・Ccに入っている人も含めて全員に返信したいのかによって宛先を注意しなければならない。
■嫌われやすい文章
・読みづらい・意味が分かりにくい文章は不快感を招きやすい。
・絵文字を多用すると相手は文章を想像しながら読まなければならず、真意が伝わりにくい。
・相手の気持ちになってちょっと丁寧に書く。
・送信、投稿前に必ず一度は読み返す(名前を間違えるのは一番NG!)
■好かれる文章
・忙しい時間の中、一目で読みやすい文章とレイアウト
・あいさつ文がある(普段やり取りのない相手が唐突に用件から入ってくると不快)
・名乗りがある(LINEのIDやアイコン画像からは相手の名前がわからないため)
・相手との距離をわきまえている
・返事を求めているかどうかが明確になっている
■ネットコミュニケーションにまつわる疑問・質問について
Q.すぐに返信すべきか?
人にふりまわされず、自分はどうしたいのかを判断して最初に宣言する。
「自分は早く返信したいので即レスするけど皆さんに即レスは求めていません!」とか
「土日はオフラインと決めているので返信しません!」
「すぐに読むけどすぐには返信できません!」など。
Q.SNSでコメントを要求されたらどうしたらいいか?
ネット上ではなくリアルな関係でその人とどういう人間関係でありたいかを考える。
相手がとにかく誰かと喋りたがっていたり、スマホ中毒・ネット中毒だったりする可能性もあるので健康を害さないか心配していると声をかけてあげることも。
Q.気遣いしすぎて投稿数が増えてしまう
個人向けではなく、みんなに対して発信するよう心掛ける。
いつまでも同じメンバーと交流があるとは限らない。その時に必要な付き合いをしていればよい。特定の人やある特定のグループにべったりと依存するのではなく、複数の人と交流するといい。実際に会った時に話をしてみてもいい。自分が思っていることはたいてい相手も同じことを思っていたりする。LINEで無料電話を使って話をするのも良い。
■子どもにスマホを使わせないで欲しい理由
スマホはインターネット上につながる「どこでもドア」で「個人情報の詰まった機械」なので、むやみに子どもに使わせてはいけない。自由に気軽にスマホを使ってもいい習慣を身につけさせてしまうと、成長してからも友達のスマホを勝手に触ってなりすましで発信したり、課金請求されるようなサイトに勝手にアクセスしてトラブルを起こすこともある。スマホには大切な個人情報がたくさん詰まっていることと、それを勝手に使ってはいけないということをしっかり教えることが大事。
 学級第9回の保育室だより(子ども達の名前はすべて仮名です)
学級第9回の保育室だより(子ども達の名前はすべて仮名です)
『もう知らなかったじゃ済まされない!ネットコミュニケーションマナー』
今回は親子スマイルネットの佐藤安南さん、鵜飼絵美さんにお越しいただきました。
映像ディレクターとしてお仕事をされている佐藤安南さんには、昨年「メディアから見た現代の子育て事情」というテーマで、一昨年は「メディアから見た現代の子育て家庭」というテーマでお話を伺いました。
LINE、Facebookなどのツールを誰もが使うようになった昨今、「ママ友とのLINEで返信の早さについていけない」など悩むママも多いため、ネットでのコミュニケーションについてお話を伺いました。
■ネットコミュニケーションにまつわる悩み・疑問
・キラキラしているママ友の写真を見て羨んだりして疲れたり、人に影響されたりしないように、SNSはやらない。以前はサークルなどの関係で朝から50件ほどメッセージが入っていたこともあるが、それを読んだりするのが大変なので抜けた。
・複数人に送られた一つのメールに対して、同じ用件なのに別の題名に変えて返信してくる人がいて異なるスレッドが立って困ったことがある。
・LINEにママ友の写真を載せて抗議されて、それまでのやりとりをすべて削除した人が周りにいる。
・昔、Mixiでコメントしなかったことを友達に怒られてやめた。
・LINEは既読が分かるから、すぐに返信できない時は読まないようにしている。
すぐ返信出来ない時にLINEをうっかり既読にしてしまったら、独身の友達と険悪になった。
・スマホをいじっていると子どもが構って欲しがる→子どもを怒ってしまう→主人に怒られる。
・結婚前にMixiをやっていたが返信が大変で指が痛くなった。
・同じ年齢の子どもを持つ女性芸能人のブログを見るように旦那に言われ、そのブログの情報と自分を比べられるのが嫌だ。
・グループLINEで「うちの子○○できるようになったよ」とそれぞれがコメントすると、グループ全員に対して返信を返さなければならず、コメント数が増えてしまって大変。
■インターネットの基本情報(総務省発表)
・世界のネット人口:34億9千万人 → これだけの人から見られる可能性がある。
・ネット利用端末:1位 パソコン、2位 スマホ・・・若い人ほどスマホ → 子どもにも教育が必要。
・インターネットの利用目的:1位 ソーシャルメディアの利用(SNS、YouTube、検索)
・ソーシャルメディアの利用目的:人とのコミュニケーション
・日本でのソーシャルメディア利用率:1位 LINE、2位 Facebook
・世界のLINE利用人口:2億人(10〜20代) → 年代によって使うツールが違う
・世界のインスタグラム利用人口:5億人(20代女性がメイン) → 変な写真は載せない!
メール・LINE・SNS → ネット上の「文字」のコミュニケーション
■インターネットでの心得
自分のペースで使えばいい(自分を主体にする)
返事をしないと嫌われるかも→なんで嫌われたくないのか、その人とどうなりたいのか?SNSをどう使いたいのかを自分から発信することも必要。実際に会ったときに宣言する。
ネット上に流れる情報は鵜呑みにしない
インターネット上に乗っている情報は間違いが多い。子育て情報、幼稚園情報など鵜呑みにしない。学校でも宿題の調べものをするのにインターネットを使用してもいいことになっているが、市や区の運営してる公式なサイトのみが許可されている(他のサイトは信用できない)。
子どもは教育されているが、親世代はネット教育を受けていない。
自分で考えて自分で決める
人とのコミュニケーションは直接話すことが大切。
グループメッセージの利用について
文字を書くのが上手な人と下手な人がいる(=誤解が生まれる)という大前提を認識すること。
おしゃべりと連絡事項の違い
LINEなどでは「○月○日に△やります!」という大切な情報を発信しても、「参加します」などのコメントが増えるほど、当初発信した大切な情報がどんどん埋もれていってしまう。
<ツールの使い分け>
・おしゃべり用のLINEグループと連絡用のLINEグループを分けて作る
・おしゃべり用はLINE、連絡用にはメールを使うなどしてツール自体を使い分ける
・どうしても使い分けできない場合は、埋もれた情報を掘り起こして再度発信する。埋もれて分からなくなった情報を放置せずにきちんと質問する。
<文章の使い分け>
・先生など目上の人を相手にスタンプ一つで返信を終わらせるのは失礼。言葉遣いを考えて文章を書く。
・大切な連絡事項は誰もが読みやすいように箇条書きにする。
■SNSを使うなら知っておきたいこと
<LINE、Facebookなどのツールが無料な理由>
私たちが個人情報を載せている(=個人情報を提供している)
↓
ライフスタイルに見合った広告が掲載される
↓
企業は広告で収益を得ている
<公開範囲の設定>
情報の公開範囲の設定をしないと、見ず知らずの誰でもが閲覧できる状態になっている。誰と誰がつながっているか等の情報が公開されることによって、オレオレ詐欺などで悪用され、自分とつながっている周りの人が迷惑を被ることもある。
海外では子どもが「自分の小さい頃の写真をインターネット上から削除して欲しい」と訴訟を起こした事例もある。親は子どもが可愛いからといって色々な写真を載せたりしがちだが、子ども自身もネットを使うようになっている。
■メールを使うなら知っておきたいこと
3種類の宛先を正しく使い分けないと個人情報漏えいにつながる。
To(読んで欲しい相手)
Cc(カーボンコピーの略:コピーとして送りたい・知らせたい相手)
Bcc(ブラインド(見えない)で送りたい相手、不特定多数に送る時などに使用)
もらったメールに返信する時も、メールをくれた人だけに返信するのか・Ccに入っている人も含めて全員に返信したいのかによって宛先を注意しなければならない。
■嫌われやすい文章
・読みづらい・意味が分かりにくい文章は不快感を招きやすい。
・絵文字を多用すると相手は文章を想像しながら読まなければならず、真意が伝わりにくい。
・相手の気持ちになってちょっと丁寧に書く。
・送信、投稿前に必ず一度は読み返す(名前を間違えるのは一番NG!)
■好かれる文章
・忙しい時間の中、一目で読みやすい文章とレイアウト
・あいさつ文がある(普段やり取りのない相手が唐突に用件から入ってくると不快)
・名乗りがある(LINEのIDやアイコン画像からは相手の名前がわからないため)
・相手との距離をわきまえている
・返事を求めているかどうかが明確になっている
■ネットコミュニケーションにまつわる疑問・質問について
Q.すぐに返信すべきか?
人にふりまわされず、自分はどうしたいのかを判断して最初に宣言する。
「自分は早く返信したいので即レスするけど皆さんに即レスは求めていません!」とか
「土日はオフラインと決めているので返信しません!」
「すぐに読むけどすぐには返信できません!」など。
Q.SNSでコメントを要求されたらどうしたらいいか?
ネット上ではなくリアルな関係でその人とどういう人間関係でありたいかを考える。
相手がとにかく誰かと喋りたがっていたり、スマホ中毒・ネット中毒だったりする可能性もあるので健康を害さないか心配していると声をかけてあげることも。
Q.気遣いしすぎて投稿数が増えてしまう
個人向けではなく、みんなに対して発信するよう心掛ける。
いつまでも同じメンバーと交流があるとは限らない。その時に必要な付き合いをしていればよい。特定の人やある特定のグループにべったりと依存するのではなく、複数の人と交流するといい。実際に会った時に話をしてみてもいい。自分が思っていることはたいてい相手も同じことを思っていたりする。LINEで無料電話を使って話をするのも良い。
■子どもにスマホを使わせないで欲しい理由
スマホはインターネット上につながる「どこでもドア」で「個人情報の詰まった機械」なので、むやみに子どもに使わせてはいけない。自由に気軽にスマホを使ってもいい習慣を身につけさせてしまうと、成長してからも友達のスマホを勝手に触ってなりすましで発信したり、課金請求されるようなサイトに勝手にアクセスしてトラブルを起こすこともある。スマホには大切な個人情報がたくさん詰まっていることと、それを勝手に使ってはいけないということをしっかり教えることが大事。