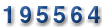2016年4月生活記録 第10期生 山本綾乃[2016年05月20日(Fri)]
現在、教育実習まっただ中!
毎朝5時に起き、クラスメイトと車に乗り合わせし登校、8時15分から11時30分まで幼稚部で実習。
午後はクラスや個別指導の繰り返しという1ヶ月間でした。
バイリンガル教育をバランスよく行っており、教育の質は予想以上に高く大変参考になりました。

(絵本が子どもの目の高さに合わせて置かれている)
幼稚部の一日
8:00 登校
8:15 朝の会 (アメリカではMoringMeeting モーリングミーティングと言います。かわいらしい響きですね)
8:30 書く時間
9:30 体育
10:10 おやつタイム
10:30 見る時間
11:00 ゲーム
11:30 給食
午後は、読む時間、算数、理科、下校
という流れです。
幼稚園部の子どもたちにとって、書くことや読むことは苦手なことかと思っていたのですが、
ここの子どもたちは自分からすすんで課題に取り組んでいたので驚きました。
その秘密は、先生の工夫にあると感じました。
まず、教室環境をそのテーマに合わせること。
例えば手紙を書くというテーマなら、教室に郵便のブースを設置する。
テーマにあった教室環境は視覚的補助となって、先生が手紙の書き方などを説明する際に
子どもたちはイメージしやすくなります。
手紙を書く手順は、まず先生がモデル例を示す、子どもたちの考えを板書する。
ワークシートには初めに絵を書き、最後に文章を書いて完成という流れでした。
体育の後には、おやつタイムがあります。その際に、アメリカ手話(ASL)による物語をYouTubeで見ます。
内容的に難しくても、子どもたちは真剣に見ていました。
ここにも秘密がありました。
大学院の講義で、見せっぱなしにしてはいけないと学んだことを思い出しました。
その都度、手話の解説を子どものレベルに合わせて説明することが必要なのです。担任の先生はそれをしっかりとなされていました。
ASL物語だけでなく、児童番組やアニメは子ども向けでありながらも、大人と子どものコミュニケーションをつなぐきっかけとなりますね。
クラスの子どもたちはとても素直で、かわいらしかったです。
毎朝おはようと走り寄ってくる子、説明を困った顔で真剣に聴く子、だだをこねる子、無表情で静かな子、おしゃべりが止まらない子など様々な子どもがいました。
メリーランドろう学校のホームページを紹介します(英文)
http://msa.maryland.gov/msa/mdmanual/25ind/html/24deaf.html
一方、講義も充実していました。
EDU 713: Language Acquisition and Cognitive Development

この言語獲得のクラスは、教育学部長でもあるガラテ・マリベル教授が担当しています。彼女は、以前来日し明晴学園で講演されたことがあるそうです。教授の書かれた英語の論文に少しつまずいていた時、日本語に翻訳された論文があると研究室が紹介してくれました。


(マリベル教授の論文の日本語訳)
ギャロデット大学の近くにあるバーガーキングが1日DEAFDAYとして、ASL一色になりました。看板やメニュー、スタッフありとあらゆる細かいものまでアメリカの指文字で書かれており、驚きました。キングも登場し、ASLであいさつしていました。
映像と写真を通してここで紹介します。
映像
https://www.youtube.com/watch?v=rkiwXm46S4k

写真




4月末は実習に加え、レポート作成の課題にも取り組む毎日でした。
秋学期最後にもお伝えした通り、大学院には試験がありません。
そのかわりに、レポートとプレゼンテーションがあるため、それらの準備を始めました。